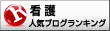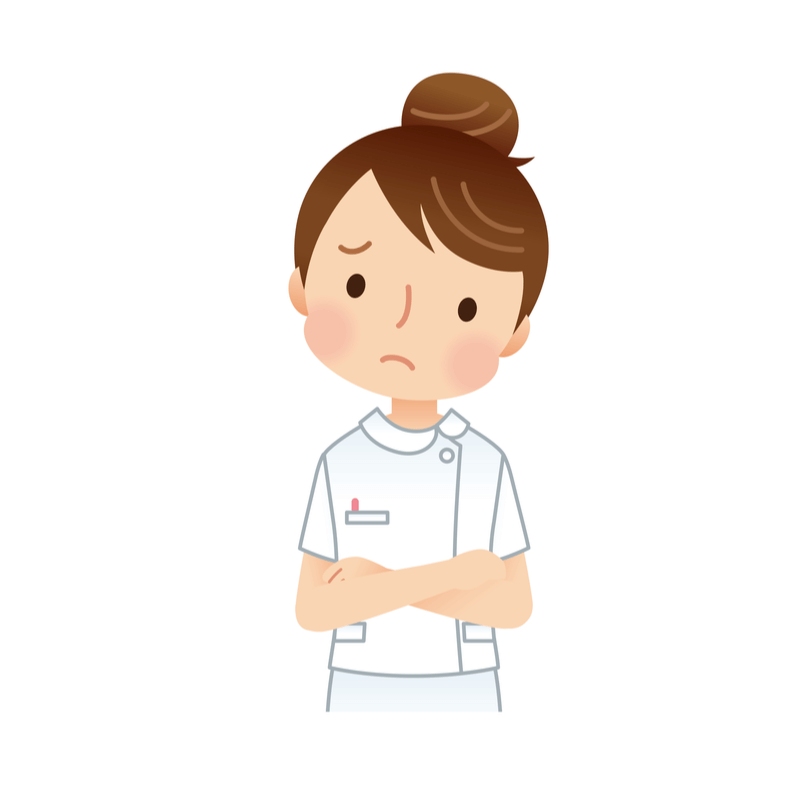こんにちは!ハロです!!
私についてはプロフィールをご覧ください。
>>プロフィール
「TKAの術後は何を観察するの?」
膝関節の手術に対してTKA(人工膝関節置換術)が行われます。
この記事では、看護師歴10年を超えるハロが、TKAについて、TKA術後の観察項目をポイント絞って説明します。
記事の最後には『知っておかないと痛い目をみる!』誰もが知っておくべき話をお伝えします。
この記事を読めば、TKA術後患者の担当になっても困らず、自信を持った看護を行えるようになります。
TKA(人工膝関節置換術)とは、術後管理と看護

TKAとは?
TKAとは【Total Knee Arthroplasty】人工膝関節置換術の略称です。
変形性膝関節症や関節リウマチなどにより変形した膝関節に対し、TKAが行われます。
損傷した膝関節部位を取り除き、代わりに人工膝関節を埋め込みます。
手術によって、術前に感じていた痛みが解消され、歩行障害が改善します。
TKA術後ポイント
TKA術後、注意すべきポイントは【後出血】と【循環・神経障害】の2つです!
それぞれ説明していきます!
後出血(ドレーン管理)
術後、思いがけない多量の出血が起こる場合があります。
後出血が起こっていないか、ドレーンからの排液量を経時的に観察する必要があります。
ドレーンからの排液量が急激に増えた場合
目安として、ドレーンからの排液量が100ml/時以上ある場合、すぐに医師に報告し対応が必要になります。
※血圧低下・出血性ショック状態に注意し、バイタルサイン測定と全身状態の観察を行います。
ドレーンからの排液量が急激に減った場合
急にドレーンからの排液量が減った場合、チューブ内の閉塞、もしくは陰圧がかかっていない可能性があります。
※ドレーン刺入部からバックまでのチューブを点検し、チューブの屈曲やチューブ内に凝血塊による閉そくが起こっていないか確認し、ミルキングを行います。
※ドレーンバック内が陰圧か、ドレーンバックの管理手順に沿って確認しましょう。バック内の排液が満タン・多くなている場合、正しく陰圧がかからないことがあります。
膝装具(ニーブレス)による循環・神経障害
術後、膝装具(ニーブレス)を装着し膝関節を固定し、患肢の腫脹や浮腫を軽減する目的で患肢をクッションで挙上します。
膝装具の膝関節固定によって、循環・神経障害が起こる場合があります。
循環・神経障害の観察項目
・足先の冷感・皮膚色
・知覚・運動障害の有無
・DVT(深部静脈血栓症)の発生の有無
→患肢の安静が長いのでDVTの発生に注意。
※母指の知覚鈍麻、足先の底屈・背屈運動に障害が起これば、腓骨神経麻痺です。すぐに医師に報告が必要です。
【大切な看護の話】TKA術後の循環・神経障害の原因は医原性

TKA術後、特に注意すべきポイントは【後出血】と【循環・神経障害】の2つです。
この2つでも声を大きくして伝えたいのは【循環・神経障害】です。
なぜなら、この障害のほとんどが医原性だからです。
要するに、自分の看護が正しく行えば防げるものであり、障害が起これば正しく看護ができていなかったことになります。
過去に私の病棟では、下肢の手術を受けた患者が術後に腓骨神経麻痺を起こし、術後管理が正しくできていたのかと、医師から注意を受けました。
一度障害が起これば、回復に時間がかかりますし、最悪、後遺症として麻痺が残ります。
このようなことを起こさないために、正しい看護知識・技術を身につけ実践しなくてはいけません。
最後に、私の話を聞いてください!
「今から処置をするといわれたけど、何を準備したらいいの?」
経験のない疾患や手術・処置を行う患者の担当になり、困ったことはありませんか?
正しい知識をもって看護を行わないと、私の病棟で起きた話のように取り返しのつかないことが起こります。
そうならないためにも、疾患や手術ごとに正しい知識や技術を身につける必要があります。
そんな時【はじめての整形外科看護】の本が役に立ちます!
【はじめての整形外科看護】は疾患や骨折した部位ごとに治療方法や患肢の固定法、日常生活動作の注意点、指導方法について説明されています。
写真がたくさん使われて説明されているので、とても見やすくわかりやすいのが特徴です。
私もわからないことや、ど忘れしたとき、本書をちらっと見て勉強・復習をしています。
さまざまな疾患を抱えた患者を受け持ちますが、必要な知識や技術をすべて身につけるのは難しい。
けれど、何もわからないまま患者を受け持つことは、大変危険で、怖いことです!
だから、わからないことをわからないままにせず、その場で解決する工夫が必要です。
【はじめての整形外科看護】はわからないことをわかるようにしてくれ、すぐに実践へと導いてくれる本です。
整形外科で働いているなら【はじめての整形外科看護】を持っておけば困ることはありません!
ぜひ、下記リンクから【はじめての整形外科看護】を購入してくだい!
自分らしい看護をするには、自分に自信を持たなければできません。
日々の不安や悩みを1つずつ解決させることが、自分に自信をつけることになります。
『わからないことが、わかるようになる』
この積み重ねが自信となり、自分らしさに繋がります。
これからも『自分らしい看護師』になるために必要な知識や考え方をお伝えしていきます!
応援よろしくお願いします!!
関連記事
>>【要点のみ解説】ORIF(観血的整復固定術)術後の看護
>>『できない』を『できる』に!看護師のアセスメントの身につけ方
>>【もう人間関係に悩まない!】性格の悪い看護師に苦しんでいる人へ、秘密の対処法をお伝えします!
ブログランキングしています!
「少しでも参考になった!」「共感できた!」という方は下記バナーを押して、応援してくださると大変うれしいです!!
![]()